今回の英検も、4級と3級(3級は現時点では一次試験)を受験した生徒さんたち、全員合格しました!
+バンドの最高は「+10」です。
ほぼ全員、余裕のある結果を出してくれました。
高い合格率のヒミツ
私の教室は、「少しでも早く英検を取ろう!」「積極的に受験しよう!」という方針ではありません。
むしろその逆です!
私は、特に小学生については、理解や応用が伴わないまま英検の級を積み重ねていくような受験には反対です(受験などで英検の級取得が必要な場合は除きます)。
それなのになぜ、私の教室の英検合格率が高いのでしょうか?

答えはシンプルです。
普段のレッスンで学んでいる内容の方が、英検より難しいからです!
「先取り」ではなく「理解の深掘り」
教室のレッスンでは、英検合格のために、何か特別な先取りをしているわけではありません。
ただ、レッスンで扱う内容が濃く、高度なのです。
英検3級程度までで確認できるのは、「簡単な理解」と「簡単な応用」まで。
一方で、私のレッスンで実践しているのは、「高度な理解」と「高度な応用」です。
たとえば、英検では選択肢を選ぶだけの問題が多いですが、
同じ範囲を学んでいる私の生徒さんたちは、
「その文法を使って自分の言葉で文を作る(話す・書く)」ところまで練習しています。
そのため、「レッスンの宿題の方が難しい!」と感じる生徒さんが多くて当然なのです。
結果として、英検の問題が「簡単」と感じられるようになります。

満点合格を目指す理由
私は生徒さんたちに、「英検でミスがあれば、それは弱点。しっかり見直そう」と伝えています。
目的は「合格」ではなく、弱点の特定と克服。
満点を目指すプロセスには、次の2つの大きな意味があります。
①弱点の早期発見
ミスの種類や原因を特定し、次の学びにすぐ生かせます。
②学習の再現性
満点を目指すことで、計画→実行→振り返り→改善の流れが身につきます。
これは英語だけでなく、他の教科にも役立つ学びの型です。
教室が目指すのは、「使える英語」
英検合格は「副産物」
英検の合格は、決して「目標」ではなく、日々の授業で育てている力の確認という「副産物」と考えています。
教室で大事にしているのは「試験のための学習」ではなく、自分の考えを相手に届けられる力です。
たとえば、レッスンでは、「写真1枚から英語の説明を組み立てる」「友だちの意見に賛成・反対を1文ずつ理由つきで返す」など、状況に応じて使えるタスクを多く取り入れています。
これらはそのままスピーキングやライティングの力につながり、結果として英検の設問にも余裕を持って対応できるようになります。
さらに、フォニックスや文法を使って、英語の4技能(読む・書く・聞く・話す)の橋渡しを常に意識して行っています。これを毎回のレッスンで回すことで、知識が「点」で終わらず、使える「線」と「面」に広がっていきます。

単なる先取りではなく「理解の深掘り」
英検合格のための「暗記」に頼らず、なぜそうなるのかを理解する過程で思考力を養い、「使える状態」に落とし込んでいます。
教室で大切にしている「思考力」をどのように育てているのか、実際のレッスン例もまじえて、詳しくはこちらのnoteでも綴っています。

「選ぶ」より「つくる」
一般的に、英検を受験している小学生には、選択式の問題では「消去法で当てている」お子さんが多いのが現状です。
これではたとえ合格していても、英語を理解していることにはなりません。
私の教室で大事にしているのは、選択肢を選ぶ英語ではなく、自分の言葉で話し・書き・伝える英語です。
私の教室では、必要な表現を自分で「つくる」力を養っています。
レッスンのなかでは一部、選択肢問題も取り入れていますが、必ず「根拠をもって正解を選ぶ」練習をしています。

努力の積み重ね
毎回、合格される生徒さんたち。
努力の積み重ねが結果につながったこと、本当に素晴らしいです。
日々の宿題やスピーキング練習、単語テストなど、どれも小さな一歩の積み重ねでした。
今回の合格は、まさにその「積み重ねの証」です。
大切なのは、ここから。
英検に合格して終わりではなく、「できる英語」「伝わる英語」をさらに磨いていくことが次のステップです。
試験で問われる英語は「入口」であり、使える英語はその先に広がる世界です。

これからも、英語を「勉強」ではなく「ことば」として使いこなす力を、その面白さを味わいながら一緒に伸ばしていきましょう。

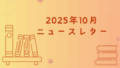

コメント