小学校英語の“限界”|7割戻した理由とは【現場のリアル】
カリキュラムを変えて7割戻した経験
こんにちは!後悔しない小学生英語、中目黒スマイル英語教室の田中彩子です。
今日は、私が教室のカリキュラムを大きく変えてみた結果、「7割を元に戻すことになった理由」についてお話しします。
日頃から保護者の皆さまからはご相談を多くいただきますが、特に、
– 「小学校でも英語をやってるから、家ではもう大丈夫なのでは?」
– 「英語教室では、どこまでやるべきなんだろう?」
と感じている小学生の保護者の方にとって、参考になる内容だと思います。
—————————–
今回の記事を、動画でご覧になりたい方はコチラ
——————————
変化の激しい時代、教材もそのままでいいの?
この10年で、子どもたちを取り巻く環境や学びの形は、大きく変わりました。

昔はうまくいっていた教材や方法も、今の子どもたちにそのまま通じるとは限りません。
時流が大きく変化し、小学校のみならず教育界でも大きな変更が相次ぐ時代です。
教育に関しては、
「これで昔うまくいったから」
「ずっと変えていないから安心」
そんな考え方は危険だと考えています。
私の教室は常に、社会の変化や子どもたちのニーズに合わせて指導法や教材を進化させていくことをモットーにしています。
そのなかで、時代の変化に合わせて思い切ってカリキュラムを見直す大きな決断をした年がありました。
小学校英語の「教科化」が大きな転換点に
その決定的なきっかけとなったのが、2020年度から始まった小学校英語の「教科化」でした。
英語は、全国の小学校で当たり前に学ぶ教科になったのです。

その時、私はまず、学校の教科書や指導要領を丁寧に確認しました。
そして、こう考えました。
「学校と同じことを教えても意味がない。
内容が重なる部分は、教室では省こう」
そうして、学校と似ている単元は思い切ってカットし、教室独自のカリキュラムを再構築。
その新カリキュラムで、新年度のレッスンをスタートさせたのです。
学校英語の「定着の弱さ」という誤算
でも、新年度をスタートさせてすぐに、違和感を覚えました。

「学校で英語を学んでいるはずなのに、その内容に関して、子どもたちの定着度が想像以上に低い」ことに気づいたのです。
たしかに、学校では英語に触れてはいます。
でも、「紹介して終わり」「ちょっと真似して話せるようになったら終わり」という授業が多く、学習が「使える知識」にはつながっていなかったのです。
つまり、私が「もう学校でやっているから省こう」と思った内容は、実際には子どもたちの中に何も残っていなかったのでした。
7割を元に戻した「軌道修正」とその気づき
この気づきを受けて、私は、その年に省いた内容のうちの7割程度を、すぐにカリキュラムに戻しました。
小学校英語に過度に期待しすぎた自分自身への反省を込めて。
しかし、気づいてすぐにカリキュラムを元に戻せたので、大きな軌道修正が成功した年でもありました。

見えてきたもうひとつの課題:学びの二極化
さらに、地域の小学校の英語の授業を見学に行って、もう一つ、重要な課題に気づきました。
それは、「子どもたちの英語経験の差が非常に大きくなってきている」ということです。
帰国子女や英語ネイティブの子どもたちは別にして、
同じ英語のクラスに、
– 学校以外で英語を学んでいる子
– 小学校だけで英語を学んでいる子
が同時に存在して、
– 学校の英語は「簡単すぎてつまらない」
– 学校の英語は「よくわからなくてつまらない」
という、2タイプの子どもたちがいるという、「両極端の問題」が起きていたのです。

「ちょうどよくない学び」が広がっている
このような「学びのギャップ」は、毎週子どもたちと向き合っている教室だからこそ、また、学校に出向いて授業参観をしているからこそ、肌で感じられる内容でした。
このギャップが広がったままでは、小学校の英語は、
皆に「ちょうどよい学び」ではなく、
誰にとっても「ちょうどよくない学び」
になってしまいます。
小学校英語の限界と、民間教室の役割
小学校の先生方は本当に努力されています。
ですが、英語指導の専門でない先生も多く、リソースが限られているなか、指導に限界があるのも事実です。
小学校の先生方に最大限の敬意を表しながらも、私は、小学校英語の現状については懸念しています。
具体的には、
– 単語は知っていても、発音が曖昧
– フォニックスや音のつながりが理解されていない
– 文法や言葉の構造を含む「言葉を学ぶことの楽しみ」まで踏み込んで教えきれていない
といった内容です。

こうした現状は、私のレッスンの子どもたちが教えてくれる「学校英語」に関する感想からも、感じられるようになってきました。
教室でしかできないことを
私は、こう考えています。
学校が「英語への入り口」だとしたら、
私たち民間の教室は、「使える力」や「伝える力」につなげる場所であるべき。

大事なのは、知識を詰め込むことではなく、子ども一人ひとりに合わせて補ったり深めたりしていくこと。
それが今の時代に求められている、民間教室の価値だと実感しています。
これからも「アップデート」し続ける教室へ
小学校英語だけでは、子どもたちの英語力に大きな差が生まれているのが現実です。
「小学校の英語は、英語を習っている子には簡単すぎて、習っていない子には難しすぎる」
という二極化の問題も確実に起きています。
私の教室では、この問題を何とかしたいと以前から考えてきました。
現在、こうした現実を踏まえて、どのレベルの子にも「楽しく・しっかり力がつく」ようなカリキュラムを再構築中です。
これからも、子どもたち一人ひとりにとって意味のある英語学習を提供できるよう、日々実践を重ねていきます。



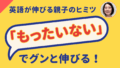
コメント